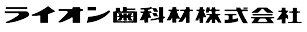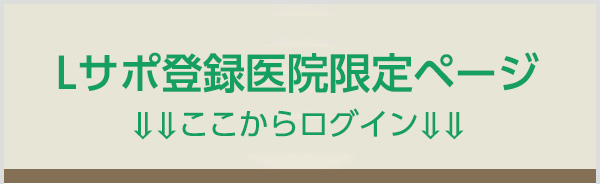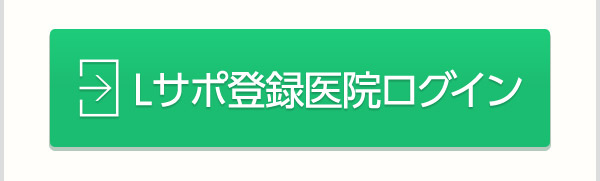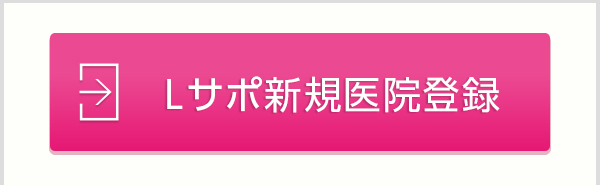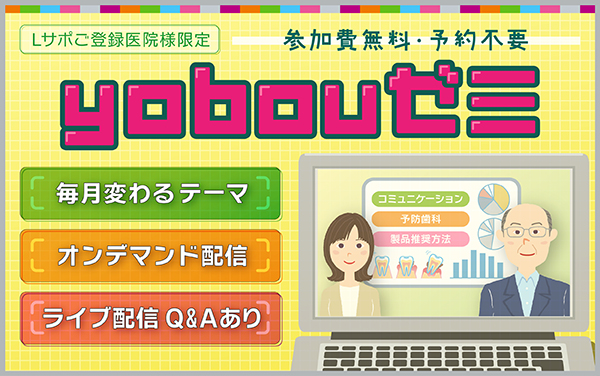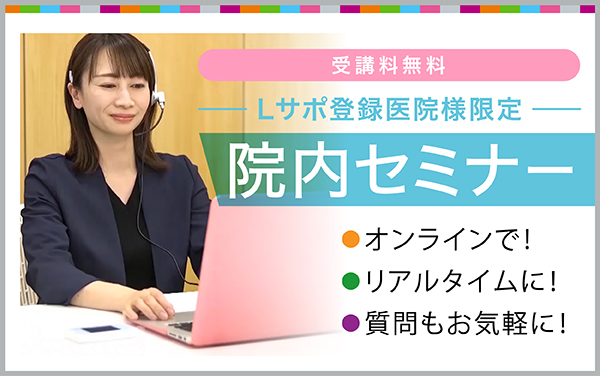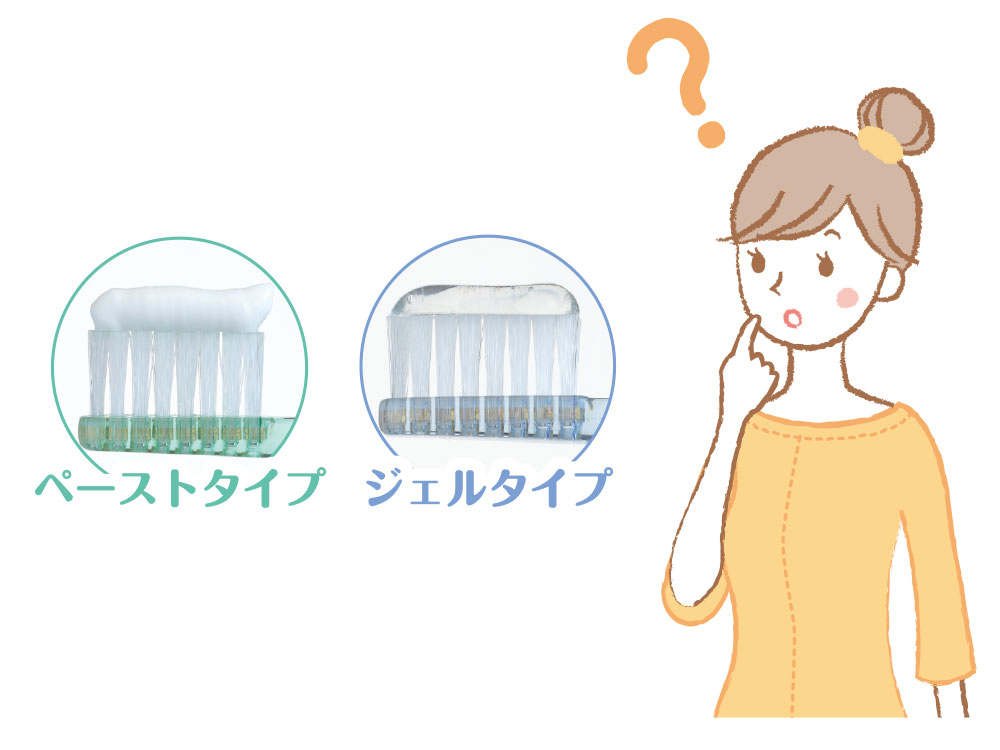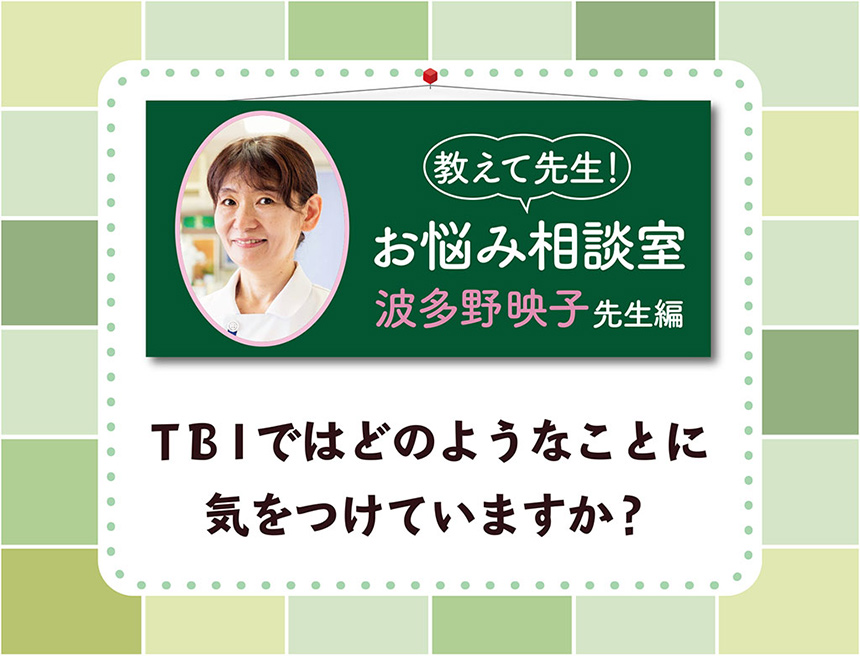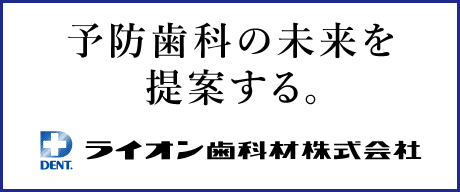口元の健康が、全身の健康と心の健康を支える源です

2025.12.3(水)
19:00~20:15
9月18日(木)受付開始
申し込み受付中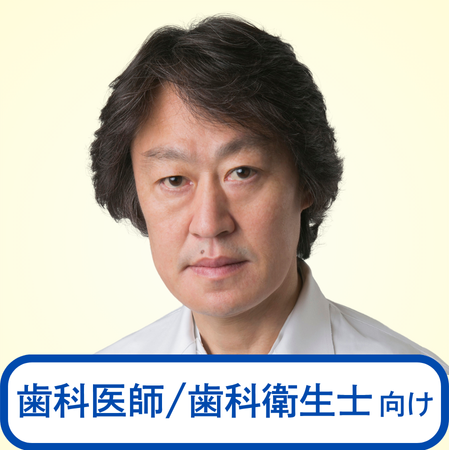
- ●講師 宮崎 真至先生(日本大学 教授 歯学部保存学教室修復学講座)
- ●会場 ウェビナー
【概要】
齲蝕に関する基礎ならびに臨床的な知識の蓄積によって、この疾患の拡大を抑制し、生涯にわたって自分の歯で食事をすることを可能とするものとなりました。その一方で、社会環境ならびに生活環境の変化は、歯質に対して少なからずの影響を及ぼすことが社会的な問題ともなってきています。口腔内に長期間にわたって歯が残存することは、咬合接触とともに飲食物などの影響を受けやすくなることを意味するものとなります。したがって、齲蝕の予防とともに、歯質の損耗の予防に対する対策が重要な課題になっています。
例えば、Tooth Wear (トゥースウェア) は、露出した臨床歯冠が何らかの原因によって損耗する疾患を総称したものです。その原因は複雑であり、咬耗、摩耗あるいは酸による影響などが複雑に関与することによって、症例によっては積極的な歯科治療が必要となります。これまで、硬組織疾患を予防する方策として、いかにしてこれを未然に防ぐかに主眼が置かれ、早期発見・早期治療が重要であるという認識がもたれていました。しかし、罹患した後にこれを進行、増悪させない処置や機能を失った後のリハビリテーションについても予防の範疇に入るものであり、この観点からあらゆる口腔疾患に対処することが大切になるものと考えられるようになっています。このように、歯科疾患の進行の抑制あるいは病的状態にまで進行した後の処置については、“予防”をキーワードとして考える必要があります。
“自分の健康は自分で守る”ことが大切であり、その意識を継続的に持っていただくためにも、適切なオーラルケア製品を選択することが大切である。そのような意識を患者と共有するためにも、プロフェッショナルケアが必須であり、これを効果的に行うことが望まれます。本講演では、患者とともに歩む未来型歯科診療について、最小限の侵襲による歯科治療について考えてみたいと思います。
★☆★略歴★☆★
1987年 日本大学歯学部卒業
1991年 日本大学大学院修了、博士(歯学)
1991年 日本大学助手(歯学部保存学教室修復学講座)
1994年 米国インディアナ州立大学歯学部留学(2年間)
2003年 日本大学講師(歯学部保存学教室修復学講座)
2005年 日本大学教授(歯学部保存学教室修復学講座)